不眠の認知行動療法について
ストレスや環境の変化に伴っておこる一過性の不眠は誰もが経験する正常な反応と言えます。しかし、長期間、不眠状態が続き、日中の集中力低下、眠気、イライラなどの症状がみられる場合には治療が必要になります。
最近になって、不眠に対する認知行動療法の効果が明らかになってきました。複数の信頼できる論文を調査した結果からは、認知行動療法は不眠に対し十分な効果があり、かつ、治療終結後もその効果が持続することが明らかになっています。ただし、不眠には様々な原因があり、全ての不眠に対して認知行動療法はお勧めできません。したがって、不眠を対象とした認知行動療法は医師の指導のもとに行うことが安全で効果があります。また、不眠に対する認知行動療法は、睡眠日誌を書く、自分の行動を変えるなどの自己努力のいる治療法です。得られる結果を信じて努力することこそ治療がうまくいくコツです。
認知行動療法は、心理教育(正しい知識を得ること)、睡眠日誌による睡眠の評価、実際の認知行動療法、斬新的筋弛緩法を組み合わせて行います。ここでは、不眠だけが主な症状であり、他の精神症状(気分の落ち込み、意欲の低下、不安など)がない場合の、慢性不眠に対する認知行動療法について簡単に説明したいと思います。
1. 必要な睡眠時間;8時間の睡眠時間にこだわらないようにしましょう。人によって必要な睡眠時間は異なります。睡眠時間が短くても日中の眠気で困らなければ大丈夫です。また、歳をとると睡眠時間は短くなります。70台では6時間以下の睡眠でも日中の眠気がなければ大丈夫です。無理に8時間眠ることはありません。
2. カフェイン、タバコ;眠る4時間前のカフェイン摂取はやめましょう。夕食時に習慣的に飲んでいる飲料にカフェインが含まれていないか確認しましょう。また、寝る前のタバコも寝付きを悪くします。
3. アルコール;アルコールは寝付きを良くする作用はありますが、睡眠脳波を取ると睡眠を浅くすることが知られています。寝付きを良くする目的で寝る間にお酒を飲むのは良くありません。アルコールは適量を、毎日ではなく、夕食時に楽しみながら飲みましょう
4. 入浴;寝る間には、身体の内部の体温(深部体温)が下がることが知られています。寝る直前に熱いお風呂に入ると深部体温が上がり、寝付きが悪くなります。入浴は寝る2時間前にすませるか、寝る前であればぬるめのお風呂に入りましょう。
5. 朝の日光とメラトニン;脳からは、メラトニンという睡眠を引き起こすホルモンが分泌されます。朝、目から光が入るとメラトニンの分泌が抑制されます。同時に体内時計のスイッチが入り、そのおよそ15時間後(夜に)メラトニンが増加し眠気を引き起こします。朝、目から光を取り入れることで、睡眠リズムが正しく調整されます。
6. 室内の照明、パソコン、スマホの光;光はメラトニンの分泌を抑制します。夜は、部屋の照明を明るくし過ぎないことが大切です。また、寝る前のパソコンやスマホは、覚醒レベルを上げ寝付きを悪くします、特にベッドに入ってからのスマホは、目からの光がメラトニンの分泌を抑制する可能性がありよくありません。
7. 昼寝;午後3時以降に昼寝をすると夜間の睡眠が悪くなります。昼寝をするなら午後3時前に、30分以内にしましょう。
8. 寝室の環境;寝室や寝具は良い睡眠のためにとても重要です。早朝に日光が強く差し込むと睡眠が途切れてしまうことがあります。その場合は遮光カーテンを用いましょう。寝具も自分に合ったものを選ぶことが大切です。
睡眠日誌と睡眠効率
(1) 睡眠日誌の書き方
行動療法では、自分を観察する科学者の態度が求められます。ここでは、睡眠について記録しますが、この記録は現在の状況や認知行動療法の治療効果を知る上で極めて重要なものです。
睡眠日誌の例
| 月 日 | 月 日 | |
|---|---|---|
| 昨晩床に就いた時間 | ||
| 寝付くためにかかった時間 | ||
| 今朝、目覚めた時間 | ||
| 目覚めてから、布団を出る までの時間 |
||
| 夜中に目覚めましたか | はい、いいえ | |
| 夜中に目覚めていた時間の合計 | ||
| 昼寝をしましたか | はい、いいえ | |
| 夕方、アルコール、カフェインをとりましたか | はい、いいえ | |
| 日中の眠気はありますか | はい、いいえ | |
| 日中の昼寝はありますか | はい、いいえ |
(2) 睡眠効率とは
睡眠効率とは、ベッドにいる時間のうち実際に眠っている時間の割合です。
睡眠日誌から計算することが出来ます
睡眠効率 =(実際に眠った時間)÷(ベッドの中にいた時間)×100
たとえば11時にベッドに入り、1時間後に眠りについて、6時に目覚めてしまい7時にベッドから出るとすると、実際の睡眠時間は6時間となり、ベッドにいる時間は8時間、睡眠効率は75%となります。
同じ6時間程度の睡眠時間でも、12時にベッドに入り15分で眠り、6時15分に目覚めてすぐにベッドから出れば、睡眠効率は94%となります。
たとえ同じ睡眠時間でも睡眠効率を上げて、眠れないのにベッドの中に長くいる状態を避ければ、寝室やベッド=眠れない場所という条件反射が、寝室やベッド=眠る場所 という条件反射に置き変わります。
なお、認知行動療法では、睡眠効率は85%以上になるよう調整していきます。最近では、睡眠効率を自動で計算してくれるアプリもあります。
不眠に対する認知行動療法の実際
不眠症に陥っている人は寝室やベッドが寝ようとしても眠れない苦しい場所だと無意識に(脳が)感じています。これが不眠を継続させる悪い条件反射です。寝室やベッドが心地よい眠りと関連する場所だという良い条件反射が出来ることが不眠に対する認知行動療法の基本です。
一般に行動療法では治療的な行為に名前が付いています。技法の名前は重要ではありませんが、技法の目的と具体的な方法を知っておくことは大切です。たとえば自分の外部にある一定の刺激(たとえば音を聞かせて餌を与えた犬が、音だけでよだれを垂らす場合、その音を“刺激”を呼びます。ここでは、寝室とベッドが“刺激”となります。不眠症では、寝室やベッドが寝ようとしても眠れない苦痛、翌日の眠気などの負のイメージと関連した“刺激”となっています。寝室やベッドを良い睡眠と関連付ける“刺激”にする工夫が刺激コントロール法です。眠れない状況でベッドにいる時間を短くすれば自然と睡眠効率も良くなります
1)刺激コントロール法
(a) ベッドでは、睡眠以外の行動をしないようにします(寝床で読書しない、テレビ、スマホを見ない)
(b) ベッドに入っても眠れない時は、いったんベッドから出て寝室から別の部屋に行きます。椅子に座って軽い読書、テレビを見るなどリラックス出来ることをしましょう(ソファで横になってはいけない)など眠れない状況でベッドにいる時間を短くします。
(c) ベッドに戻るのは、眠くなってからにしましょう
下の図は、眠れないままベッドの中で過ごしている状態を示しています。
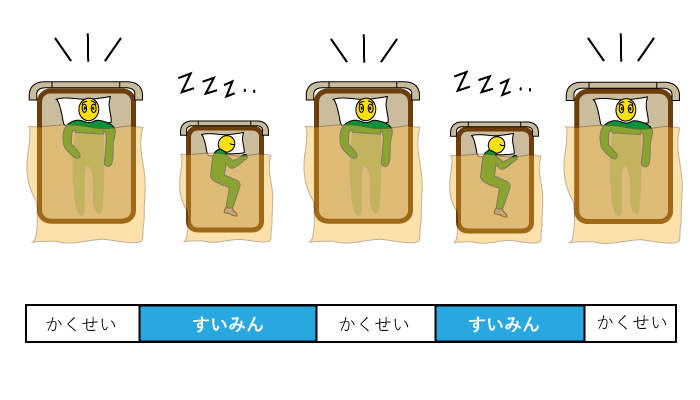
横棒の青い部分が睡眠がとれている時間帯、白い部分が眠れない時間帯を示しています。この図では、眠れない時間もベットで横になっています。
刺激コントロール法では、ベッドの中で起きている時間を減らすために、眠れない時は、寝室から出るようにします(下図)。こうすることで、睡眠効率が上がり、ベッドと寝室が心地よい眠りと関連付けられるようなります。
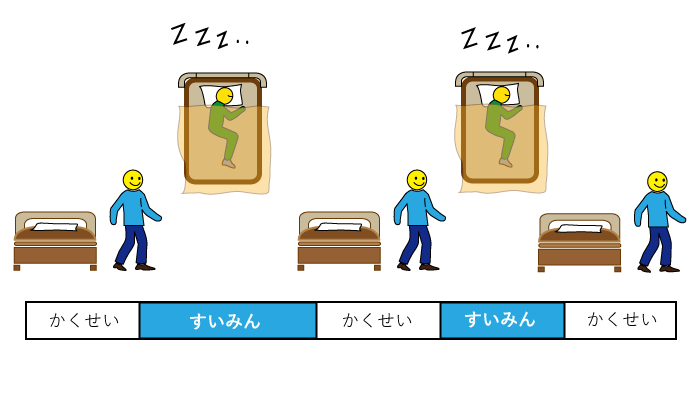
2)睡眠制限法(睡眠スケジュール法)
眠れない状態でベッドにいる時間を出来るだけ短くすることが大切です。ます、睡眠日誌で実際に眠っていた時間(1週間の平均睡眠時間)に30分を追加した時間をベッドにいてもいい時間とします。そこから、ベッドに入る時間、起きる時間を決めます。決めた時間は必ず守るようにしましょう。この方法では、初めはベッドに入る時間が今までよりも遅くなります。また、昼寝はしてはいけません。
漸進的筋弛緩法
筋肉の緊張と弛緩を繰り返し行うことにより身体のリラックスを導く方法です。身体の上の筋肉から下に向かって順次行っていくため。漸進的(ぜんしんてき)という難しい名前が付いています。
ベッドに入る前に椅子に座って行いましょう、全部で10分~15分ほどかかります。
筋肉に5秒間力を入れ緊張させ、15秒間脱力・弛緩します。力が入った状態と、リラックスしている状態の差を感覚でわかることが大切です。
1.
両手の緊張、弛緩
膝の上に手のひらを上に向けて置きましょう。両手をギュッと5秒間きつく握ります、次に手を開いて力を抜きます(15秒) 下図
2.
両腕
両手を握り、拳を耳に近づけ、曲った上腕全体に力を入れ5秒間緊張させ、その後15秒間脱力・弛緩します。
3, 背中
ボートに乗ってオールを漕ぐ時の、オールを引きつけた姿勢で、肩甲骨を引き寄せるように力を入れ、その後、力を抜きます。
4. 肩
座った姿勢から、両肩をあげ、肩を強くすぼめます。
5. 首
右側に首を傾けます。左側も同様に行います。
6. 顔の筋肉
口をすぼめ、顔全体を顔の中心に集めるように力を入れる。
その後、顔の力を抜く(口は軽く開く)
7. 腹筋
座った状態で腹筋に5秒間力を入れて、その後力を抜きます
8. 足
座った状態で足を延ばします。つま先を伸ばし、足の下側の筋肉を緊張させます。次に、足の力を抜いて弛緩させます。足指手前に曲げ、足の上側の筋肉を緊張させます、次に足の力を抜きます。
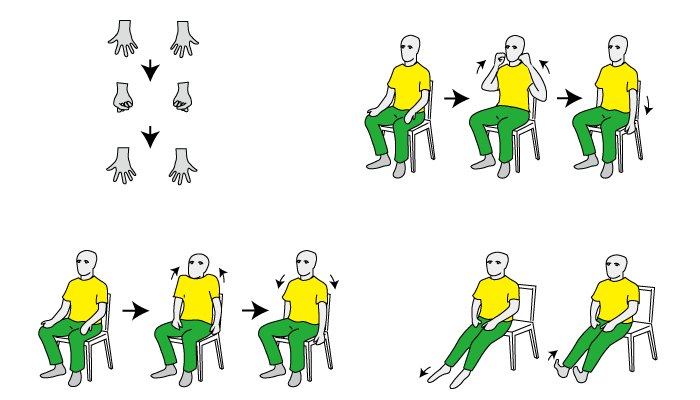
睡眠リズムを正しくしよう
体内時計
体内時計は、視床下部の視交叉上核に存在します。視交叉上核にある細胞(時計細胞)は、時計遺伝子を持っているため、蛋白を合成し、結合し、また分解されることを約24時間周期で繰り返しています。そして、この蛋白合成、分解のリズムを信号として身体全体に1日のリズムを知らせます。体内時計は、朝、目から入った光によってリセットされ1日のリズムを作ります。図では、目から入った光が視交叉上核(時計細胞)を経由してさらに室傍核を経由して全身に伝達される様子を示しています。時計細胞は、日中には交感神経の活性化、コルチゾールの分泌、深部体温(脳温)の上昇などによって日中に人を目覚めた状況に維持します。メラトニンは目覚めてから14〜16時間ぐらい経過すると体内時計からの指令が出て分泌されます。 徐々にメラトニンの分泌が高まり、その作用で深部体温が低下して、休息に適した状態に導かれ眠気を感じるようになります。メラトニンは、体内時計によって分泌がコントロールされていますが、光によっても分泌が抑制されるため、就寝前にメラトニンが上昇する時に強い光を浴びるとその分泌が抑制され睡眠が妨げられてしまいます。
メラトニンの作用
就寝前になりメラトニンが分泌されると(就床時刻の1~2時間前)、急速に覚醒力が低下します。このため、私たちは夕食後にすっきり目が覚めていても、就寝時には急に眠気を感じるようになります。朝方になると覚醒作用を持つ副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の分泌が始まります。また、脳の温度が自然に高くなります。覚醒前にこうした準備状態が整って朝の目覚めがよくなります。メラトニンは睡眠を促進する作用を持ちますが、明るい光の下では分泌が停止します。静臥して熱放散を促し、メラトニン分泌を妨げないように消灯をした暗い部屋で休むことは、睡眠をサポートする生理機能の力を最大限に引き出す上でも大事なことです。
体内時計をリセットしよう
朝、決まった時間に起きましょう朝食をとることでリズムを整えましょう
午前中に十分な太陽光を浴びましょう
午前中か、夕方までに運動しよう
睡眠不足の時は、休日の午後に短い昼寝をしましょう
寝る前のブルーライト、あるいは強い光は避けましょう
明るい光は、メラトニンの分泌を抑制し眠りを妨げます。照明は暖色系の照明を用い、明るくしすぎないようにしましょう)
寝る直前に暑いお風呂に入ること、寝る直前のアルコールは睡眠にとって良くありません。飲酒をする場合は適量を夕食と一緒にしましょう。
メラトニンを使いリズムを整える
メラトベル(メラトニン)
6-15歳の神経発達症(ADHD、自閉スペクトラム症)の入眠困難に用います。神経発達症では、寝つきが悪く、朝起き不良になることがあり、日中の眠気を訴えることもあります。寝る前に服薬する方法と、夕方から服用する方法があり、使い方については医師と相談する必要があります。成人の神経発達症にも有効な可能性がありますが、成人への投与は日本では認可されていません。
ロゼレム(ラメルテオン)
メラトニン受容体刺激して、睡眠を改善します。また、投与時間によっては正しい睡眠周期を取り戻すことが出来ます。